プライベートで写真を撮るならスマホがあれば十分でしょう。
ちょっとしたスナップ写真やSNS用の写真はもちろん、旅行の思い出や子供の成長記録としてもクオリティ的な不満はありません。
しかもアプリのおかげで写真の管理も便利です♪

それに比べて、かつて主流であったフィルムカメラはどうでしょう?
撮った時点では写り具合はまったく分かりません。
カメラ屋さんに持ち込んで現像してもらう必要がある上、できあがるまでには数日待たされます。

そうそう、今思えば懐かしいなぁ。
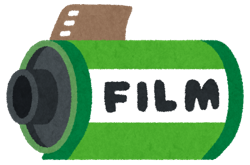
そんな不便なフィルムカメラなど今や誰も興味を持たないだろう・・と思いきや、実はそうでもないのが面白いところ!
レコードで音楽を聴く人や 旧車好きの人がいるように、フィルムカメラでの撮影を楽しむ人たちがたくさんいるのです。
今回は巷で話題の「トイカメラ」と呼ばれるフィルムカメラに注目し、一番有名なモデルともいえる 「LOMO LC-A」を紹介します。
こちらのカメラは"独特の写りが撮れる"ということで世界中にたくさんのファンがいるんですよ♪
LOMOって?
"トイカメラといえば LOMO"と言われるくらいこのジャンルでは有名です。
「LOMO」というのはロシアの光学機器メーカーの名称ですが、同社が製造した「LC-A」というカメラのことを指す場合もあります。

実はロシア製の「LC-A」は2005年で生産中止になっています。
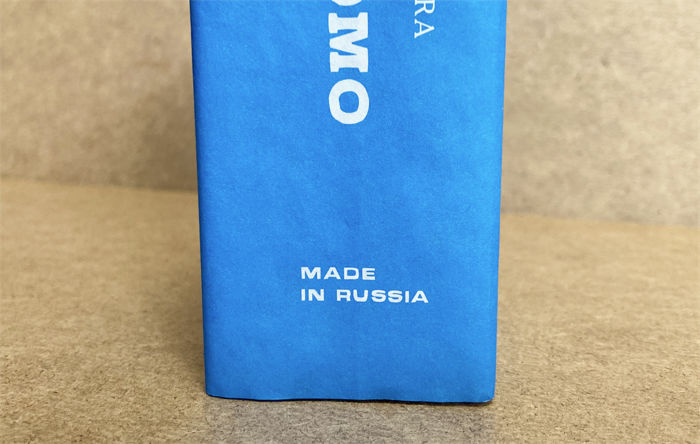

LOMOってもう手に入れられないの?

LOMO人気は世界中に広がってましたから・・
2006年にロモグラフィー社によって生産が再開されたんです!
ロモグラフィー社に変わってからのモデルは「LC-A+」と呼ばれており(末尾に+が付く)、中国にて生産され、機能的にも若干の変更が加えられています。
「LC-A」の紹介
LOMO「LC-A」の特徴を細かく見ていきましょう。
写真はロシア製だった頃のモデルになります。

本体以外には説明書(英語表記)とストラップが同梱されています。

「LC-A」のサイズはとてもコンパクトですが、手に持つと結構ズッシリしています。

| サイズ | 幅107mm × 高さ68mm × 厚み40mm |
| 重量 | 250g |
カメラ中央部分が出っ張っているのが外観上の特徴で、ここにキャラクターの「ロモ蔵」がプリントされています。

もちろん背面には(デジカメのような)液晶画面などありません。
ファインダーをのぞいて撮ることになります。


中央部分(正面に向かって)左サイドには「絞りレバー」があります。
このカメラは絞りを設定して使いこなすのが難しいため、(写真のように)「Auto」に合わせている人が多いようです。

逆サイドにあるのは「距離レバー」です。
被写体までの距離(m)を大まかに設定することでピントを合わせる仕組みです。

中央右サイド上部には「感度ダイヤル」があり、ISO25/50/100/200/400の5段階で設定します。

中央下部のレバーをスライドすると、レンズとファインダーのカバーが開きます。
開いた状態にしてはじめてシャッターが切れます。
ちなみに搭載されるレンズは「MINITAR1 2.8 32㎜」です。

カメラ底面には電池をセットします。
「LR44」という形式のボタン電池が3つ必要です。

フィルムを入れるときは「巻き戻しクランク」を引き上げて本体裏のカバーを開きます。

このカメラで使用するフィルムは35mmのタイプです。

シャッターボタン右横には「フィルムカウンター窓」があり、こちらで撮影枚数を確認します。
フィルムの巻き上げについては手動でレバー操作します。

フィルムを入れて各種設定を済ませたら撮影してみましょう!
最初はいろいろ戸惑うかもしれませんが慣れれば問題ありませんよ。
スマホのように"なんでも機械任せ"ではなく、自分の手で操作することが楽しいのです♪

慣れたらマニュアル操作の魅力にハマりますよ!
LOMOの写真の特徴
LOMOで撮られた写真には独特の発色があり、写真の四隅が暗くなるのが特徴です。
このなんともいえない雰囲気が魅力的で、世界中にLOMO愛好家が増えています。



四隅の現象は「周辺光量落ち」というものです。
別名「トンネル効果」とも呼ばれています。
こんな味のある写真、スマホでは撮れませんよね。
カメラ屋に持ち込んで現像してもらうのに時間はかかりますが、出来上がりを楽しみに待っていましょう♪

あえて「不便さ」を愉しむカメラです。
新しい趣味としていかがですか?
まとめ
最近のスマホやデジカメと比べたらLOMOには不便な点が多々あります。
しかし「あの独特な写り方」を見てしまうと「LOMOで撮影すること」そのものが楽しくなってくるです♪
写真の現像にかかる時間も気にならなくなり、むしろワクワクして待ってられますよ♪
「LC-A」は生産中止になっているため入手は困難かもしれませんが、気になる方はメルカリなどで探してみてはどうでしょう。
後継機である「LC-A+」ならネットショップでも見かけますが、こちらも新品の在庫は少なくなってきましたね。



